新卒でインフラエンジニアとして大手に内定した私の新卒就活についてのメモ【エンジニア就活】
Contents
はじめに
この記事はいち情報系大学院生がエンジニアとして大手(5大SIerのどこか)にインフラ部署のSE職として内定するに至るまでのエンジニア就活の流れを事実ベースで書いただけです
個人の主観が多いので、ほんの参考程度に見ていただきますようお願いします
就活前までのIT経験について
私は大学に入る段階で既にIT系のエンジニアになりたいとは漠然と考えていたので、いろんなITの勉強を大学生から始めました まずはエンジニア経験の遍歴を以下に綴ります
なんでわざわざこれを書くかというと、結局何が一番エンジニア就活の面接で刺さったかって、「ITが大好きだよ」ってことを具体的なIT経験をもってアピールできた事だったからです
いきなり面接の話ですが、面接では私はだいぶ口下手で周りの優秀な方々のように理路整然としたコミュニケーションは出来ませんでしたが、以下のように継続して好きでIT分野の勉強を続けて来たことだけは良く伝えられたと思いますし、良い就活の結果が出たのはそれが大きいと思います
遍歴(要約)
| 遍歴 |
|---|
| 大学2年:AtCoder開始 |
| 大学3年:クローラー開発アルバイト(10ヶ月) |
| 大学4年:簡単なアプリ開発・自宅サーバーの勉強 |
| 修士1年 : サーバー運用保守アルバイト(1年) |
大学2年(AtCoder)
友人に勧められて競技プログラミングを開始
→ これが初めての自主的なプログラミング学習
約1年で茶色(最高レート561)まで到達
得られたこと
- プログラミングの基礎知識 (手を動かすのがいちばんプログラミング学習に効く)
- 授業で学んだアルゴリズムの腹落ち(計算量・データ構造とか)
大学2〜3年(開発系アルバイト)
約10ヶ月、東京のクローラー開発の会社でスクレイピングを主としたCLIアプリ開発を経験
AtCoderでプログラムを書くのが楽しいと思えるようになり、今度は開発を実務で学んで見たいと思い5社くらいにアルバイトとして応募 → ありがたくも唯一OKをくれた東京の会社でアルバイトを10ヶ月した
経験したこと
- Gitのコード管理経験
- Rubyによるプログラム作成・修正(バグ修正/クラス共通化)
- MySQL操作・SQL作成
得られたこと
- チーム開発の書き方
他の人にも読みやすい、変更が簡単なコードを書くことを練習できた - エンジニアのコミュニケーション能力 = 分からない点を端的に伝える能力
入ったばっかのときは上手く出来ず超大変だったが、超大事な能力が身についた
これができないとエンジニアとしてやって行けないと思う
大学3年(趣味での簡単なアプリ開発と自宅サーバー)
簡単なプログラミングを勉強してから、普段のネットサーフィンで不便だと思ったことをアプリ開発(大したクオリティじゃないけど)をしてみたり、それを動かす基盤のlinuxサーバーを立ち上げて色々勉強を始めた
大学4年〜修士1年 (サーバー運用保守アルバイト)
意外にも約1年自宅でのLinuxサーバー運用でサーバー・ネットワーク側をいじる方が面白く感じたことから、
実務の運用保守を経験したいと思い、また別の東京の会社でアルバイトを始めた
経験したこと
一般的な保守
- Web/メールサーバーの証明書更新(Apache、Postfix/Dovecot 設定変更)
- DNS設定変更(Route53 / BINDなど)
- サーバートラブル対応(原因調査→設定変更→検証の流れの経験)
簡単な運用保守システムの作成(Grafanaでサーバー状態の可視化)
- 複数サーバーのリソース使用率を横断で可視化する仕組みの設計
- プレゼン→構築→運用テストまで通しで実施
得られたこと
- オンプレ/クラウド双方の運用フロー理解
- 小さな要件でも設計→構築→運用の一連を経験
- システムの説明を誰でも分かる形に落とし込む難しさの理解
- 手順書・ドキュメント整備の重要性(再現性)
その他取得した資格
- LPIC-1
- AWS Certified SysOps Administrator – Associate (SOA-C02)
就活前までの活動を振り返って思ったこと
私が働いていた上記2つのアルバイト先では、きちんと大体1年くらい働くと責任の大きめなシステム構築や設計といった上流寄りの工程を任せて頂けるようになります
このときの経験は特に大手企業の縮小版のようなものなので、面接で問われる職業理解としてもとても強力なエピソードができます
何もこういった自主学習が無い状態で就活がスタートとしていた場合、インターン選考の段階でコミュニケーション能力不足でふるいに落とされてまともに選考が通らなかったと思うので、本当に勉強やっといて良かったです
大学生のアルバイトの選択肢って居酒屋とか接客とかレジ打ちとかたくさん選択肢はあると思いますが、やっぱり将来なりたい職業に生きる仕事を軸にアルバイトを選んでも良いんじゃないかと思いました
そういうお仕事を見つけられたらお金も稼げるし自分磨きにもなって就活でも生きるし一石二鳥です
就活開始 (インターンと本選考)
5月くらいで就活が始まったら、2週間以上のOJT型インターンシップに片っ端から応募して、夏、冬、春全てで長期のSEとしてのインターン経験をしました
就活の時はアプリレイヤーよりサーバー以下のレイヤーの技術に興味があったので、基本的にはクラウド・オンプレ問わず広くサーバーインフラのエンジニアとして応募しました ※実は冬は研究開発寄りのインターン
どこのインターンも構築や要件定義などの上流工程の経験が出来たので、アルバイト先のような中小企業では経験できないプロジェクトが出来てとても良い経験だったと思います
本選考ではインターン先以外の会社にいくつか応募を出して、面接で落ちたりマッチングが合わなかったりしましたが、最終的にはインターン経由での面接オファーを頂いた会社で内定を決めました
面接で意識したアピール内容
私が特に面接官の方に刺さったなと思うトピックは以下のとおりです
・インフラエンジニアになりたい理由 (ITインフラの安定稼働を支えたい)
これについては面接官の方も首を立てに振って共感してくれました笑
サーバーのアプリケーションってちょっとしたことですぐ止まるんですよね
アルバイトでもDNSサーバー周りのトラブルで管理していたほとんどのwebやメールサーバーが通信できなくなって、散々になっているのを目の当たりにしました
自宅サーバーで動いてるアプリでも気づいたらエラーコード吐いたりネット配線周りで止まってることがよくあって、システムが動いているサーバーの安定稼働って本当に難しいなってとても実感したし、だからこそ自分は真に止まらない安定したインフラの構築や運用保守がやりたいんだとサーバーインフラをやりたい理由がちゃんと伝わる説明をしました
今の時代アプリ開発はやりたい人はいても、インフラレイヤーを積極的にやりたいって人はあまり多くないと思うので、こういう動機はなおさら面接でも刺さると思います
・IT技術が大好きなこと(ITを勉強してること)
最初にも言いましたが、 これもやっぱりエンジニアをやる以上は超絶大事なマインドですよね
情報系の人がエンジニアになれる割合が高いのは、コンピューターサイエンスの知識があるのはもちろんですが、こういった具体的にやった経験があることで、本当にエンジニアをやりたいんだなってことが面接官に明確に伝わるからだと思います
経験したことの規模は面接ではあまり問われませんでした(メガベンチャーは別)
まあ所詮学生だし職業経験なんて無いし当然といえば当然
私はこういったエンジニアの場数をたくさん踏むことが自分に本当に向いてるか分かると考えたので、学生のうちからたくさんITの勉強やって来て、
結果として進路として間違ってないしむしろもっとやりたいというマインドになったので良かったし、他の情報系の学生の方と比較しても大きな差別化ポイントにもなって一石二鳥だったと思います
最後に伝えたいこと
長々と書いてしまいすみません、最後に私が今回の記事で一番言いたかったことを書きます
「エンジニアになりたいなら、Wantedlyとかでエンジニア系のバイトしろ 多分文系でもエンジニア就活が上手くいくぞ」ってことです
以上です
上手くまとまってない記事で申し訳ないですが、最後まで読んで頂いてありがとうございました
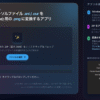





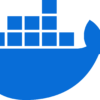
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
この記事のトラックバックURL
nyaa
情報系の大学院生
いろいろな記事を書きます
新着記事
: 音楽ゲーム
【Sparkle Shower皆伝】EPOLIS中伝から2年かかった皆伝までの成長記録メモ
皆伝...やっと取れた...歓喜!!!! 長かった...EPOLIS中伝からこの ...: パソコン/IT関連
Windows用のアニメカーソルを簡単にMacで使えるためのアプリを作った【Mousecape】
カーソルの変換がめんどくさ過ぎるのでアプリで効率化した 近年マウスカーソルは様々 ...: その他
新卒でインフラエンジニアとして大手に内定した私の新卒就活についてのメモ【エンジニア就活】
はじめに この記事はいち情報系大学院生がエンジニアとして大手(5大SIerのどこ ...: パソコン/IT関連
理想の分割スペースキーボードが欲しかったので初めて自作したメモ【自作キーボード DK6064】
はじめに (自作キーボードを始めた動機) 私はHHKB Professional ...: サーバー
おうちサーバーにはミニPCが最適解だというお話【自宅サーバー】
はじめに 皆さん自宅サーバー興味ありますでしょうか 自宅サーバーやりたいなと思っ ...タグ
Contents